業務効率化やコスト削減への取り組みを行いながら、需要の拡大を目指すEC事業者に注目されているのが、WMS(倉庫管理システム)です。
店舗数を拡大するとともに注文数も増えていくなか、入庫や出庫などの倉庫業務を手作業で継続すると、在庫差異や出荷ミスなどのトラブルも多く業務負担が減りません。
倉庫業務の最適化は、EC物流において重要な改善テーマの一つ。WMSは、そんな悩みを解決する強力なツールとして多くのEC事業者が注目しています。
ではWMS導入を検討すると、実際にどのような成果が期待できるのか?そもそもWMSって何?そんな疑問を感じている担当者も多いでしょう。本記事では、WMSの基礎知識からEC事業での活用メリット、導入時に注意するべきポイントまで分かりやすく解説します。
 楽天最強翌日配送とは?ラベルの取得と活用|楽天市場で売上UP!
楽天最強翌日配送とは?ラベルの取得と活用|楽天市場で売上UP!
 楽天スーパーロジスティクス(RSL)とは?サービスの仕組みからメリット・導入手順まで詳しく解説!
楽天スーパーロジスティクス(RSL)とは?サービスの仕組みからメリット・導入手順まで詳しく解説!
WMS(倉庫管理システム)とは?
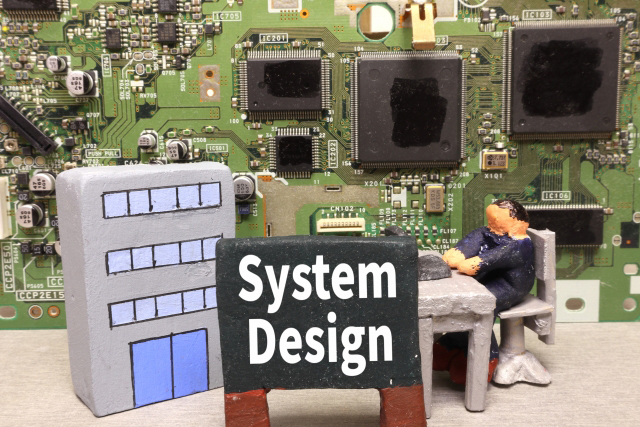
WMSとは「Warehouse Management System」を略した物流用語で、日本語では「倉庫管理システム」と呼ばれています。
倉庫やバックヤードをはじめとする、物流センターで行う商品の入荷から保管・出荷・棚卸など、一連の物流業務を支援する役割を担い、倉庫管理を行うシステムの総称です。
WMSは倉庫管理の業務効率化を考えている多くの企業で導入され、EC事業者のみならず、小売業・卸業から製造業と、幅広い事業者に採用されているシステムです。ハンディターミナルやスマートフォンなどのデバイスを使用して、商品に付属されているバーコードやQRコードを読み取り、検品や在庫管理を行います。
商品情報を読み取ってシステムに取り込むと、商品が倉庫内でどのように保管されているのか、商品情報を正確に管理できます。
倉庫在庫を適切に管理する作業は、企業の正確な資産管理ともつながるので、WMSの運用は非常に重要です。WMS導入・運用は、EC事業者にとっても、販売やネットショップの在庫管理と密接な関係性をもっているといえるでしょう。
倉庫管理システムと在庫管理システムの違い

EC事業における管理業務には、いくつかのシステムが存在します。「在庫管理システム」「基幹システム」そして「WMS(倉庫管理システム)」が広く認知されているシステムです。
名称としては認識していても、それぞれの違いは明確に分からない方も多いでしょう。これらは管理対象と役割がすべて異なります。では、実際のところ、何が違うのでしょうか。
| 倉庫管理システム(WMS) | 倉庫内の入出庫から棚卸・帳票管理全般(倉庫内に限定) |
| 在庫管理システム | 自社で扱っている在庫状況を可視化する(倉庫外含む) |
| 基幹システム | 事業における「商流」を管理するシステム |
EC業務でよく言われる「在庫管理」とは、入荷から受注、出荷までの全体に関わる在庫移動情報を把握・管理することを指しています。在庫管理と倉庫管理は混同されがちですが、WMSのように、倉庫内に限定した「倉庫管理」と在庫管理システムに含まれる「在庫管理」は、管理対象と目的が異なります。
WMS以外のシステムについても役割を理解しましょう。
基幹システムは企業の事業活動を表す
基幹システムは、企業の基幹業務を管理するシステムです。「生産管理」「人事給与」「会計」「個人情報」などの情報が盛り込まれ、事業活動の中核を担っています。企業における決算数値などの財務諸表は、基幹システムから出力・確認するといえば分かりやすいかもしれません。
「商流(お金の流れ)」に重点を置いた基幹システムにも在庫管理機能はありますが、倉庫在庫の動きを管理する倉庫管理システムとは、管理する内容が異なります。企業で統一された基幹システムでは大枠の在庫管理しか行えず、商品の入出庫など実際に倉庫で発生する物の動きは管理できません。
実際の在庫の動きを管理し、資産として計上する棚卸の作業を行うのは、WMS(倉庫管理システム)の役割です。
在庫管理システムでネットショップの在庫を把握する
WMSは、倉庫内の在庫管理に限定されたシステムです。在庫管理システムは、倉庫外も含めた在庫情報を管理するシステムです。在庫管理システムは、基幹システムと連動している企業が多い傾向にあります。
ネットショップにおいて、商品の在庫状況を把握したり入出荷の管理を行ったりと、効率的に商品を補充し、販売や発注をサポートするのも、在庫管理システムの大きな役割です。在庫管理システムの主な項目には、取扱商品の商品マスタ、入出荷に関する情報、ネットショップ内の受発注情報などが該当します。
小規模運営のネットショップであれば、システムを導入せず、在庫管理をエクセルやスプレッドシートなど、手作業で行っている場合も多いでしょう。在庫数量管理や商品の詳細情報管理などを、業務効率化する目的で開発されたのが「在庫管理システム」です。
WMSが担う倉庫での役割

WMSは倉庫内で正確で効率的な作業を行うために、業務全般を支援するシステムで、主に4つの機能があります。ハンディターミナルと呼ばれる端末を使い、商品個別についているバーコードを読み取って、登録・管理を行います。
| 入荷管理 | 商品が倉庫に入荷した後の、入庫処理全般(受け入れから棚入れ)の作業を行う |
| 在庫管理 | 在庫保管や処理に関わる作業、保管商品の在庫照合・棚移動指示などを行う |
| 出荷管理 | 販売時や倉庫間移動時など、商品の出荷と出荷に付随した業務を行う |
| 棚卸管理 | 倉庫で行う棚卸データの取り込みと結果の照合や検証、棚卸結果の反映を行う |
この4つの管理機能を使い、倉庫内の商品について「どこに何があり、どのように動かすべきか」を管理し、倉庫内の効率化を目指します。倉庫管理業務を改善するのが、WMSの役割といえます。
入荷管理(倉庫に商品を受け入れる作業)
発注した商品が倉庫に入荷した際に行う、受け入れ・検品・棚入れまでの一連の作業が「入荷管理」です。入荷は倉庫で商品管理を行う最初の作業で、この正確さがその後の管理業務に影響する重要な工程です。
商品が納品される際に、仕入れ元が発行した伝票や納品書に書かれた情報をあらかじめWMSに取り込んでから、実際に入荷した内容と照合して、差異がないか確認し、正確な入荷情報を登録します。
この時点で商品検品も行い、商品に瑕疵がないか・販売できる状態かを確認するのも重要です。
倉庫では、商品管理を行う際に必要な、共通の管理番号(JANコードや商品コード)が書かれたラベルを商品に貼り、棚に格納します。そのラベル発行や格納(棚入れ)作業も、この入荷管理に該当するものです。
入庫処理の具体的な業務内容については、別記事の「【入庫とは】物流における重要な業務|倉庫管理との関係性も解説」も参考にしてください。
在庫管理(倉庫在庫の管理作業全般)
倉庫に入荷した商品を棚入れしたり、保管していた商品を出荷したりする際、いずれの場合も「在庫管理」機能を使い、在庫情報を記録します。在庫情報を照会する・移動指示を行う・あらかじめ設定していた商品の賞味期限や使用期限を警告する、これらもすべて「在庫管理」で行います。
特に頻繁に使用する在庫照会はCSV形式に対応している場合が多く、商品単位や品番、ロケーション(棚番号)などの必要項目を一覧として印刷したり、データ更新を行ったりすることが可能です。なお、抽出可能な項目は、WMSによって異なります。
「何を」「どこに」「どのくらい」保管されているかの基本情報から、保管状態や保管期間、賞味期限や使用期限などの詳細な情報が、在庫管理機能を使い把握できる仕組みとなっています。
倉庫での作業は効率化が重要視されるので、在庫管理機能は精度や情報の出力スピードが非常に求められる機能です。
出荷管理(ネットショップの受注にともなう作業)
倉庫間の商品移動や取引先への返品、販売など、さまざまな理由から、倉庫で保管している商品を、梱包・出荷する作業に関連する機能が「出荷管理」です。
システムより指示を受けた出荷依頼情報を取り込み、在庫引き当て、出荷指示、ピッキング、検品、梱包、送り状印刷や明細表の印刷などの発送処理といった一連の工程を、出荷管理機能を使って行います。
ネットショップに入った注文を受注し、お客様の元に届けるまでの全工程もこの機能に該当します。ただ在庫を発送するだけでなく、納品時期が古い商品から順番に発送するなどの先入先出(さきいれさきだし)ルールがあれば、WMSを使ってその情報をコントロールする場合もあるでしょう。
出荷作業は入荷作業同様に、正確にスピード感をもって、効率的に行うのが重要なので、複数の出荷作業が重なった場合など、優先順位を見て柔軟に対応しましょう。
棚卸管理(倉庫内の棚卸結果をシステムに反映する作業)
半期や1年間、事業によっては毎月など、企業が定めたサイクルに沿って、倉庫内にある実在庫を計上し、WMS上の在庫数と一致しているか確認します。これが「棚卸管理」業務です。棚卸は、企業としての利益を確認するためにとても重要な作業です。
在庫として計上されている商品は漏れなく附け上げて、WMSに実在データを取り込むのが棚卸の作業で、附け上げにはハンディターミナルなどの端末を使用し、商品に貼られているバーコードを読み取ります。
取り込んだ実在庫データをシステム内の在庫データと照合し、万が一差異があった場合は、WMSで履歴を追い、原因の検証を行います。検証を行い、日ごろの管理業務に改善点はないのか、どうすれば差異が防げるのかなど今後のシステム運用に活かすようにしましょう。
棚卸の結果は、最新の在庫情報としてWMSシステム内で更新されて、基幹システムとも連動します。
WMS導入がもたらすメリット

WMSが倉庫管理業務においてどのように活用されるのかを確認してきましたが、WMSを導入した場合、実際にもたらされるであろうメリットには、どのようなものが考えられるでしょうか。主に以下の項目が想定できます。
- 作業でのミスが減り、作業効率が上がる。
- 作業効率化で、費用削減が可能となる。
- 作業における手順が標準化・ルール化できる。
- 倉庫の物流能力が向上するきっかけになる。
- 倉庫内の状況を可視化できるようになる。
WMS導入は、倉庫業務全体の精度向上を実現し、効率化につながります。そして、業務全体を可視化することで業務に携わる全員がメリットを理解し、倉庫内の作業方法標準化への理解が深まり、標準化にともなって運用するルールを共有できるでしょう。
ここからは、WMS導入がもたらすメリットの詳細を解説します。
ミスの軽減と作業のスピードアップ
倉庫内では、非常に多くの作業を行うため、細かいチェック作業も頻繁に発生します。商品検品に始まり、ロケーション・数量など、チェック項目を理解して手動運用するのはとても大変です。
WMSならば、ハンディターミナルなどの端末で、バーコードを読み取って在庫登録したり在庫情報を更新したりするので、手作業と比べても正確で素早い処理が可能です。
倉庫ではピッキングなどにかかる歩行時間が最も多いとも言われています。WMSを使えば、ロケーションを考慮したピッキング作業が計画できるので、倉庫内を最短距離で移動するなどの効率化を実現できるでしょう。それは、入出庫の作業にかかる時間の短縮につながります。
ベテラン作業員の業務知識に依存することなく、均一の作業精度が維持できます。
作業効率化による費用削減
倉庫業務は、作業工程が複雑で時間のかかる内容が多いので、アナログメインでは人件費や倉庫内の設備運営費の負担が大きくなりがちです。WMSを導入することで作業工程を減らせれば、新たな人員配置を行い、作業効率化が目指せます。
工程に対して配置する人員を減らした分は、ほかの必要な業務にあてるなど見直しましょう。適材適所で人員配置ができれば、業務全体の底上げを図ることも可能です。
これまで多くの人数を配置していた工程を見直せるので、人件費の改善が実現します。作業効率化が業務改善につながり、倉庫内の設備運営費の削減も期待できるでしょう。
倉庫の物流能力が向上する
これまで手作業で行っていた倉庫内の管理業務を、WMSの導入によって効率化できるのはこれまでにも述べてきたとおりですが、人件費などの経費面だけでなく、倉庫における物流業務そのものをレベルアップできるようになります。
クラウド型のWMSを採用している倉庫であれば、インターネットに接続してどの場所からでも、最新の在庫情報を確認可能です。あわせて作業実績も把握し、状況に応じて臨機応変に物流管理者をサポートできます。
結果的に、倉庫での対応力が上がり、物流能力の向上につながっていくでしょう。
作業手順が標準化される
システムを活用すれば、バラバラだった作業手順が標準化されます。WMSの導入で業務を見直し、作業手順が標準化されていれば、仮に欠員など人員トラブルが発生して経験の浅い作業員が急遽入っても、同じレベルでの作業が可能となります。
それまではベテラン作業員に依存していた、属人化しがちな実務作業を、担当者の変更に左右されず行えるようになるので、人件費の見直しともつながるでしょう。
商品の入出庫は、ショップイベントや季節ごとの需要によって大きく左右されます。システムを活用すれば、時期によって変動する需要にも適宜対応できるようになるでしょう。
リアルタイムに進捗状況を可視化できる
WMSでは、ハンディターミナルなどの端末を使って商品を認識するために貼られたバーコードラベルを読み取り、実績をシステムに反映させる仕組みとなっており、バーコードを読み取ってデジタルチェックを行います。
システムへの反映も時間差が少なく、リアルタイムで在庫状況が確認できます。そのため、作業時でも常に最新の在庫状況を確認でき、状況に応じたスピーディな対応ができるのです。
WMSを活用すれば、現場状況を迅速に把握し、問題が発生しても素早く解決可能です。そこで得た知見をもとに適宜システム機能をアップデートできるのも、魅力の一つでしょう。
WMS導入にもデメリットはある

WMS導入にはさまざまなメリットが考えられますが、デメリットもあります。
システムの導入目的は最初からきちんと設定しましょう。導入目的が曖昧だと、期待した効果が得られません。これは、システム導入で何を実現したいのか、どのような効果を期待するのかなど、システム導入によって目指したいゴールが明確に設定されていないために起きることです。
WMSは倉庫管理システムなので、単独で使用することは少なく、導入時には多くの場合既存の基幹システムとのデータ連携が必要です。基幹システムとWMSの連携では、両者にシステム改修コストが発生します。
システム導入にはコストがかかります。特にWMSは倉庫全体の改修が必要で、自社の基幹システムとも連携させる非常に大きなシステムなので、導入を進めるにあたっては、社内での事前周知が必須です。社内各所の協力なくして、新システムの導入はありえません。
実際に運用がスタートした後も、定期的な見直しが必要です。商流は時代に合わせて変化し、商流が変われば、物流も変化する必要があります。企業には多くのシステムがあり、すべてが連携することで最大限の効果を発揮しますので、システムのアップデートは必要不可欠です。
WMS導入の注目点

例えば、社内で新規にWMSを導入する場合、社内稟議を経て導入するケースがほとんどでしょう。その際稟議書では、発生するであろう経費や導入経緯、導入によってもたらされる成果を自社の事情に置き換えて考え、得られるメリットをしっかりと伝えなければなりません。
実際にWMSの導入を検討する前に、何が必要なのか、譲れない項目を洗い出し、自社にとって最適なシステム導入に向けて、導入に携わる部署全員でミーティングを行い共有します。導入前に、WMSで行う業務の再確認や、問題点の整理も必ず行いましょう。
関係各所に向け、WMSとは何か、事前に理解を深めてもらうのはとても大切です。周知する手間を面倒に感じて適当に行うと、導入後に関係先と連携が取れず、かえって業務効率が低下する、拠点ごとで作業格差が生じるなど、逆効果になる危険があるので注意が必要です。
WMS導入に関するプロセス

ではWMS導入に向けて、どのように進めていくべきなのでしょうか。WMSの導入や現システムとの連携を検討し、実際に導入するまでにはさまざまなプロセスが存在します。導入プロセスを理解し、把握してから進めると、実際に稼働する際のトラブルを最低限におさえられます。
- WMS導入に向けた計画案を策定する。
- WMS導入にあたり、共有するための資料を作成する。
- WMS導入予定の倉庫の整備を行う。
- WMSに移行するデータを準備する。
- システム移行への受け入れテストを行う。
- 受け入れテストの結果を踏まえたマニュアルなどの環境を整備する。
- 担当者への教育など、事前研修を実施する。
- 運用リハーサルと実働に向けた最終作業を行う。
- 本番稼働を開始する。
新規システムの導入は、社内外問わず、システム立ち上げに関わるすべての担当者の協力や連携なくしては成立しません。導入に向けたプロセスについて確認しましょう。
WMS導入に向けた計画案の策定
まずはWMSを導入するにあたり、導入に向けたプロセスを資料にまとめます。準備から稼働までの期間は限られているので、現実的で周知しやすい内容が求められます。
| 計画案に記入する項目 | 内容 |
|---|---|
| 導入の経緯・概要 | WMS導入の経緯や、WMSについて簡潔に触れる |
| 導入スケジュール | 導入までに行う作業工程と各スケジュール |
| 導入準備の分担 | 導入準備の役割分担と各リーダーの任命 |
特にスケジュールと、役割分担、各工程の責任者は明確にしておく必要があります。関係各所にはこのタイミングでしっかりと情報を共有し、どの担当者も疑問なく準備がスタートできるようにします。丁寧で分かりやすい作業フローを作成しましょう。
また、稼働前に万が一問題が生じた場合に、新システムを止めて旧システムに切り戻すケースを想定して、どんな状況で切り戻すかなどの基準や判断を行う担当者もあらかじめ決めておきます。
WMS導入に向けた倉庫内の整備
WMSのシステム導入ではさまざまな機器が倉庫に新しく設置されます。倉庫内のインフラ整備も必要になるので、この機会を使って倉庫内の準備をしっかり行い、稼働後に作業しやすい環境を整えましょう。
- インフラ整備のための機器設置場所の確保・ケーブル工事
- ロケーション設定のための倉庫内レイアウト決定、荷物の仮置き場や通路の確保
- 倉庫内レイアウトの変更にともなう在庫移動など、新ロケーション準備
- 現在倉庫で使用している管理システムのデータ移行準備
- 新たに必要となる什器や備品の手配
- 倉庫で担当するスタッフに向けた事前研修、作業方法の周知徹底
倉庫は、WMSが本格的に稼働した際に実務作業を担う場所なので、倉庫の事前準備は細かく行いましょう。
WMSへのデータ移行
現在倉庫で保有している在庫データを、導入するWMSに移行します。ここでは、基幹システム保守を担当している社内のシステム部門と、WMSを提供するシステム会社との連携が重要です。
社外の担当者も入って進めるので、より丁寧な作業情報の共有を行い、認識に違いが起きないように、ミスなくデータの移行作業を行います。
稼働後は、社内にある基幹システムやEC部門で使用しているシステムと連携するので、この段階でエラーなど起きないか、しっかりと確認しましょう。エラーが出た場合は原因究明を行って稼働前に解決し、本番稼働当日にトラブルが起きないよう準備します。
WMS導入と実働開始
システム稼働はいきなり本番に入らず一度リハーサルを行い、スムーズに導入作業が行えるか、エラーなどは起きないか、最終確認をしましょう。この段階で、最終的に本番稼働を行うかの切替判断を行います。
WMSは非常に大規模なシステムなので、導入・稼働当日は一定時間倉庫の作業を止める必要があります。ネットショップの出荷業務停止なども想定されるので、受注が少ない時期や倉庫の稼働時間外を選択し、システムの切り替え作業を行いましょう。
EC業務においては、システム稼働直後のトラブルを防止し作業検証を行いやすくするために、稼働開始日の出荷処理件数は通常より少なくするなど、あらかじめ調整するとよいでしょう。
稼働開始日は、システム担当者やネットショップ担当者など、倉庫以外に勤務する担当者も倉庫に待機し、不測の事態に備えておきます。
WMS導入で成果をあげるには

WMS導入、稼働開始から一定期間が経過したタイミングで、稼働状況に関する情報共有の場を必ず設けましょう。ここまでの課題や解決事項があれば整理し、関係部門で対策を講じます。導入したシステムが少しでも早く機能するように、検証もきちんと行います。
定期的に業務内容を見直し、WMSが活用されている部分とそうでない部分を洗い出す作業と必要に応じた改善作業を行って、より自社に最適なシステム環境の維持を目指しましょう。
必要に応じて担当スタッフの研修を行い、適宜、知識のアップデートを行うと効果的です。そのなかで必要な項目は、しっかりマニュアルに落とし込んで、精度の高いマニュアルを維持します。
ネットショップにWMSを活用する場合、EC業務の担当部門との意思疎通は、ネットショップの顧客満足度にも影響するでしょう。EC業務担当者は定期的に倉庫へ行き、情報共有と問題点の解決を図ります。
システムは導入して終わりではなく、商流に合わせた定期的な見直しを行う必要があります。システム提供側のアップデートも適宜発生するので、導入時と同じく、関係部門と協力してシステム改修に対応しましょう。
導入したWMSが安定稼働を持続するよう、常に検証とアップデートを継続します。
WMSと一元管理システムの連携
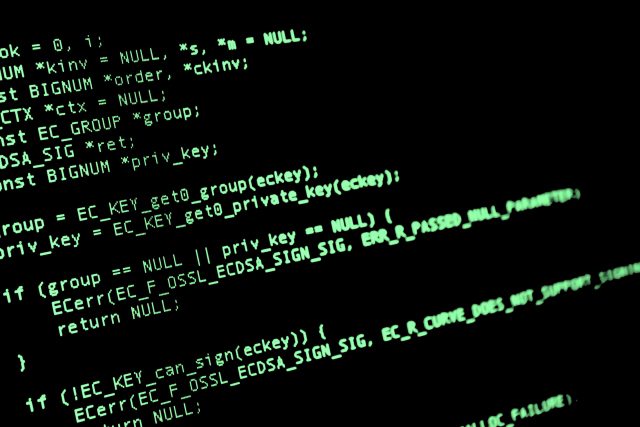
WMSは単独で効果を発揮するシステムではなく、社内にあるさまざまなシステムとの連携が重要です。WMS導入を機に倉庫の管理体制を見直せば、ネットショップを複数運営に拡大したり、取扱規模を増やしたりと、利益拡大につなげる環境が整うきっかけとなります。
現状使用している在庫管理システムが、WMS導入により効果的に運用できるのかどうかあわせて見直すのもよいでしょう。
WMSと連携可能な一元管理システムを導入すれば、倉庫管理の機能をさらに高めることが期待できます。システム導入には、初期投資にかなりの経費がかかるのも事実ですが、WMSをより効果的に運用するために、一元管理システムとの連携は検討するべきです。
複数倉庫連携ができる一元管理システムTEMPOSTAR(テンポスター)の導入を検討しよう!

TEMPOSTAR(テンポスター)には、WMSと連携できる機能が搭載されています。
TEMPOSTAR(テンポスター)の「外部連携オプション」は、TEMPOSTAR(テンポスター)が正式に連動していないモール・基幹システム・WMS・POSなどの外部システムとの自動接続を目的として、TEMPOSTAR形式の各種CSVについて自動連携を図る仕組みです。
外部連携オプションを使ってWMSと連携すれば、倉庫と在庫管理システムがつながり、次のような機能が活用できます。
- 複数倉庫(拠点)との連携 マルチロケーションに対応
- 複数倉庫に分散している在庫をTEMPOSTAR(テンポスター)で管理
- ネットショップの受注に対して、自動で配送拠点(倉庫)を選定
- 主要な倉庫システムとの連携に対応
倉庫・WMSへの出荷指示データや、倉庫・WMSからの出荷実績データの受け渡し効率化・自動化が実現し、出荷実績をもとに、連携先モール・カートへの出荷報告、注文者への発送連絡メールを自動送信することが可能です。
詳しくは、TEMPOSTAR(テンポスター)の複数倉庫連携機能を参考にしてください。
EC事業の利益拡大を目指すならWMS導入の検討を!

EC事業の拡大を考えているネットショップ事業者は、注文数が増えるにつれて、手作業では在庫のズレや出荷ミスといった課題が発生しやすくなります。そんな悩みを解決する強力なツールとして、WMSは円滑なEC物流の大きな一助となるでしょう。
WMS導入にあたり、取り組まなければならないプロセスは非常に多く、コストもかかります。しかし導入をきっかけに既存の社内システムや、これまでアナログで行ってきた倉庫業務を大きく見直すきっかけとなるのは間違いありません。
WMS導入で、どんな成果が期待できるのか?そもそもWMSって何?そんな疑問を感じている担当者はこの機会に理解を深め、ぜひWMS導入実現に向けて業務改善を進めましょう。



